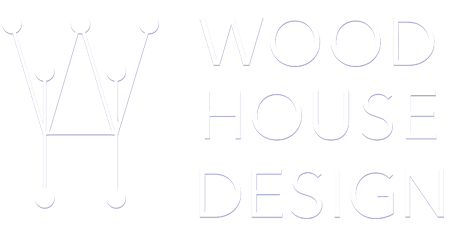度々くり返すが、私はT-バックについてほとんど何も知らない。T-バックの歴史、T-バックの効能、T-バックの動向など、知っておくべきことは山ほどあるはずだが、私が知っていることといえば、T-バックの形状が「Tに似ている」ということくらいである。しかし、前回のT-COLUMN執筆からこれを書いている現在に至るまでほぼ1週間、私はT-バックのことばかり考えている。はっきり言って、この1週間に限って言えば、日本で一番T-バックについてちゃんと考えている者は、他でもないこの私ではないか。それくらい、私は寝食を惜しんでT-バックについて深く多面的に考えているのだった。
それというのも、T-COLUMNの当面のテーマをT-バックにしようと決めてしまったからだ。
私は後悔した。T-バックに何の興味もないのだ。もちろん知識もない。それなのにT-バックについて書くなんてあまりにも無謀だ。そもそも、なぜ私はT-バックについて書こうとしたのか、それすらも分からなくなってしまった。
私はT-バックという果てしない荒野を彷徨い歩いた。歩いたというより、肉塊を引きずるようにして這うような感覚に似ていた。T-バックの荒野では、鉛色の空に乾いた風が吹きすさび、生気を失った枯草が絶えず不規則にたなびいていた。ときおり遠くから聞こえてくる雷鳴と私の荒い息づかいがシンクロし、それが不協和音となって私の鼓動を一層激しくした。私は異国に放たれた赤子のように不穏な佇まいで、とにかくおぼつかない歩を進めるよりほかなかった。私は左右の目をひん剥いて甘い果実を探したが、こんな乾いた場所に口にできそうな果実など、どこにも、そして永遠に存在しないように思われた。行き場を失った私の感情はやがて激しい慟哭へと変わったが、その声もむなしく風音と雷鳴にかき消されるのみであった。私は神を呪うような思いで地面を一掴みし、水分が蒸発しきった泥の粒子を口にした。シャリシャリと音をたてて噛むと、ただ不快な歯触りだけが口の中に広がった。このとき、私は初めて自分が絶望の淵に立っていることを自覚した。と同時に、ある音が無意識のうちに私の口をついて出てきた。私の鼓膜をわずかに震わせたその音は、まぎれもなく「wikipedia」だった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Tバック
これが、T-バックの世界だ。私はえらいところに来てしまったものだ。第3回で、こんな内容になるとは思いもよらなかった。これもすべて、T-バックのせいである。T-バックは、人を不可解な世界へと導く不気味な装置だ。
はたしてこれが下着と言えるだろうか。