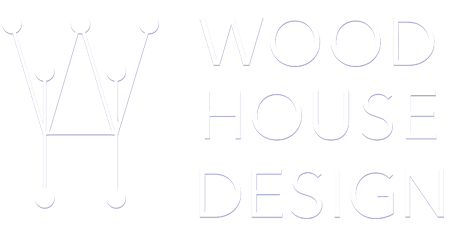かつて、おばあちゃんという存在があった。
おばあちゃんは、あらゆることを知っていた。衣服のたたみ方から病気の治療、その土地に伝わる民話から男女のかけ引きのことまで、何でも教えてくれた。まだ乳歯を余すほど幼かった者たちは、おばあちゃんに何でも質問し、そのたびに語られる小話のひとつひとつに惹きこまれ、少しずつ世界を広げていくことができたのだった。まるで泉のように知恵が湧きだすおばあちゃんの博識、それを、かつて幼かった者たちは「おばあちゃんの知恵袋」と呼んだ。
月日は流れた。
幼かった者は大人になり、そして年老いた。気がついたら自分たちがおばあちゃんと呼ばれる年齢になっていたのだ。あっけにとられて、立ち尽くすしかなかった。しばらく呆然としていたが、ふと知恵袋のことが気になった。かつてのおばあちゃんのように、自分にも立派な知恵袋が育っているだろうか。体をひねって右の肩甲骨のあたりをさすると、中にはたくさんの知恵が詰まってぱんぱんになっていた。この年になるまで、知恵袋のことなんか目もくれず、がむしゃらに生きてきた。思い返せば本当にいろいろなことがあった。ずいぶん泣いたこともあったが、むしろ楽しむことに一生懸命の人生だった。その生きた証が、いつの間にかぱんぱんになった知恵袋そのものだったのだ。もう自分は幼くはない。この知恵袋を幼い者たちへ分け与えるときが、ついにやってきたのだ。どこかに幼い者がいないだろうか。
顔を上げると、そこには人垣があった。しかし目の前には自分と同じくらいの年齢のおばあちゃんしかいなかった。目の前のおばあちゃんをかき分けて辺りを見回しても、目に入ってくるのはやはりおばあちゃんだ。おばあちゃんたちはそれぞれ思い思いの遊戯に興じており、やっていることは幼い者のようであるが、見た目はやはりおばあちゃんである。ほとんどの世帯が核家族という現代にあっては、知恵袋の中身を受け取ってくれる幼い者たちがいないのだった。かつて幼かったおばあちゃんは嘆いた。
「わしの知恵袋を、右の肩甲骨をどうにかしておくれ」
そんなこと言われても、まわりの者はどうしようもないのだった。なぜなら、そこにいるおばあちゃんたちは皆一様に、知恵袋をもて余しているからだ。
おばあちゃんは、知恵袋とともに墓に入ることを考え、途方に暮れた。
そのとき、誰かにポンと右の肩甲骨を叩かれたような気がした。ふり返ると、そこに一人の青年が立っていたのだった。
「ワタシガ ドウニカ イタシマス」
この青年こそ、他でもない若き日のジミー・ウェールズ、後のwikipedia創始者だったのである。こうしてジミーは、おばあちゃんの右の肩甲骨にビジネスチャンスを見い出したのだった。
かつて、おばあちゃんという存在があった。そして今では、wikipediaがある。
Wikipediaとは、いわば「おばあちゃんの言霊」である。だからこそ、私はwikipediaでT-バックについて調べることに違和感を覚えるのだ。
「バックスタイルがのう、T字型でカットされたデザインになっておってな、外形がアルファベットのTの字に見えるじゃろ。だからその様に名付けられたんじゃよ。」
こんな言霊は、いやだ。